『法律』と『技術』と『国際性』
を兼備した知識及び経験の豊富な専門家集団
弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK は
日本弁護士1名、日本弁理士46名(特定侵害訴訟代理人:16名)、博士資格者14名
(理学:6名、工学:2名、医学:1名、保健:1名、農業:2名、学術:1名、法学:1名)、
中国弁護士、中国弁理士等の多数の専門家を擁する大規模・国際・総合特許事務所です。

驚異的な低価格で、ご自身で検索し、ご自身でブランド化する、
AI(人工知能)を駆使した画期的なSelf Trademark Filing Serviceを
提供させて頂きますので、ご活用下さい。
Business戦略参謀を標榜する
高度の戦略性に基づいた
高品質のリーガル・サービス
世界で有力な各国特許事務所 / 法律事務所との強固なネットワークを構築した高い信頼性
日本の大動脈をなす中核都市に
太平洋ベルト知財戦略構想
を実現!
あなたのネーミングを驚きのブランドに!
弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK は
日本弁護士1名、日本弁理士46名(特定侵害訴訟代理人:16名)、博士資格者14名
(理学:6名、工学:2名、医学:1名、保健:1名、農業:2名、学術:1名、法学:1名)、
中国弁護士、中国弁理士等の多数の専門家を擁する大規模・国際・総合特許事務所です。

国際競争で加速する知財のグローバリゼーションに対応する11の各国支援室体制を構築し、
日本人の弁理士や弁護士等のロイヤーズ、及び各部門のスタッフとが中心となって、
世界各国の顧客の皆様に質の高い国際的なリーガル・サービスを提供させて頂いております。
当特許事務所は、1976年の設立以来、「顧客の皆様に最大限の満足と利益を提供する。」という基本理念のもと、皆様の知的財産活動をより広く、より手厚くサポートすることを目指して参りました。そして、「東京本部」、「名古屋事務所」、「大阪本部」、「広島事務所」という日本の大動脈をなす中核都市に特許事務所を構築し、『太平洋ベルト知財戦略構想』を実現いたしました。
顧客の皆様には、当事務所のこれら四拠点を基幹として、時代を先取りした、先進的でユニークな、高度の『知的財産戦略リーガル・サービス』を提供させて頂きますので、是非ともご活用くだされば幸いです。

当特許事務所は、弁理士・弁護士等のロイヤーズを含む専門スタッフからなる優秀かつ充実した人材を擁し、クライアントのご満足を第一に考えた迅速かつ高品質な知的サービスを提供しています。
また、当特許事務所は世界各地の知的財産権に関する専門家(弁理士・弁護士)と長年の協力関係を築いています。アメリカ・ヨーロッパ・アジア・オセアニアをはじめ、数多くの著名な法律・特許事務所と強力なネットワークを有しており、クライアントにワールドワイドなサービスを提供することができます。
私達は専門家として最適なサービスを提供できるように、所内外の研修を通じて、常にレベルアップを図っています。


当特許事務所は、「東京本部(港区浜松町)」、「大阪本部(北区南森町)」、「広島事務所(中区立町)」、「名古屋事務所(中村区平池町)」の4拠点を構築して、日本全国ならびに世界中のお客様からのご依頼・ご相談に対応しております。
また、全4拠点では、高機能・高セキュリティのWEB会議システムを完備し、全国・世界中いかなる地域からのご依頼・ご相談にも、各案件に最適なメンバーを拠点/部門の枠を超えて選抜し、当事務所の総力を結集して対応しております。
知的創作活動によって日々生み出される発明・考案・商標・意匠・著作物等の知的財産について、世界各国の特許事務所との幅広い強固なネットワークを駆使して、国内外での権利化業務に加えて、各種係争対応・権利活用などの知財コンサルティング業務を行っております。
近年、世界中で特許の重要性が高まっています。日本における特許出願件数は、年間約30万件前後で推移しており、世界中から日本へ特許出願がなされています。
特許・実用新案
他社との差別化および価格競争下の利益の安定性等の観点から商標の重要性が増しています。マーケットのグローバル化に伴い、全世界で統一されたブランドの確立が望まれます。
商標・意匠
当特許事務所は、翻訳業務及び外国出願業務サービスを提供致しており、世界各地の知的財産権に関する専門家(弁理士・弁護士)と長年の協力関係を築いています。
外国・知財翻訳
当特許事務所では知的財産の権利化だけではなく、権利活用フェーズにおいても、企業の事業戦略上重要な提言を行うなどの「知財アドバイザリー」業務を行っております。
知財アドバイザリー
過去の実績から最新のものまで私たちの活動をご紹介します。
メインメニューに関係リンク集のページを開設しました。このページでは国内外の知的財産に関するサイトへのリンクをまとめています。日本国特許庁をはじめとする知的財産の関係省庁、裁判所、各種の社団法人・財団法人、各学会・協会、さらに、関連する様々なデータベースなどを網羅的に掲載しております。「知
無料知財セミナーを4月24日に開催いたします。今回のセミナーのテーマは、意匠の外国出願に関する内容となっております。セミナーでは主要国の意匠制度の紹介、および国際意匠出願制度のメリット・デメリットについて解説いたします。ご参加はどなたでもご自由にしていただけますが、事前の登録が必要となってお
このページでは、各専門チームへの簡単な紹介をまとめています。当事務所では、外国における知的財産、大学・学術機関・スタートアップ企業・中小企業の皆様の知的財産、IT・バイオ・農業の分野における知的財産、模倣等による侵害を受けている知的財産について、専門家で構成されるそれぞれの分野の専門チームを組織
インドネシア支援室に、模倣品対策に関する記事を追加しました。インドネシアは東南アジアの中でも近年特に発展が著しく、世界第4位の人口と高いGDP成長率を誇る今や東南アジアでのビジネスに欠かせない大きな市場となっています。また、インドネシアは現在GDP17位、2040~50年には日本を抜いて4位にな
東京本部
〒105-5129
東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービルディング南館29階
TEL:03-3433-5810(代)
e-mail: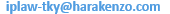
大阪本部
〒530-0041
大阪市北区天神橋2-北2-6
大和南森町ビル
TEL:06-6351-4384(代)
e-mail: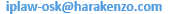
名古屋事務所
〒453-6109
愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12
グローバルゲート9F
TEL:052-589-2581(代)
e-mail: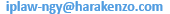
広島事務所
〒730-0032
広島市中区立町2-23
野村不動産広島ビル4階
TEL:082-545-3680(代)
e-mail: