「著作権」を簡単に説明すると、著作物を利用しようとする人に、利用を許可したり禁止したり出来る権利です。
近年、情報化の進展とともに著作権保護の必要性が高まっています。また、ブロードバンドの普及とデジタル化の進展に伴って、今後さらに新たな種類の著作物が開発され流通していくでしょう。
このような状況において、著作権に関する法的紛争も多様化・複雑化していくことが予想されます。社会の中で著作物が果たしている役割を理解し、適切に保護することが国の文化の発展につながります。
当特許事務所では、「著作権を得るためには何か手続が必要なの?」、「著作物を無断で使ったらどうなるの?」など著作物・著作権に関するみなさまのご質問やご依頼に、専門スタッフが迅速かつ丁寧に回答・対処させていただきます。
著作権支援室長 弁理士 武田 憲学 <大阪本部>
目次
初めての方へ
著作権法の今
情報化社会が進み、インターネットによってあらゆる情報に簡単にアクセスできるようになった現在、著作権法は重要な意味を持っています。
かつては、クリエイター(著作者)といえば、作家や芸術家、音楽家であり、彼らによって生み出された作品(著作物)は、マスメディア(出版社や放送事業者、レコード会社等)によって伝達されていました。
現在では、SNSを利用することによって、誰もが自分の作品を簡単に世間一般に向けて発信でき、また誰もがマスメディアを介さずそれらにアクセスし、その評価を発表することができます。
このように誰もが簡単に情報を発信し、アクセスできるという状況に加え、誰もが簡単にコピー&ペーストや画像や映像の加工処理ができるようになった現在、著作権の問題はあらゆるところに潜んでいるといっても過言ではないでしょう。
著作権法の目的
著作権法は、クリエイター(著作者)の作品に対する権利と有益な情報を社会に流通させ、ひいては文化を発展させることの調和を目的としています。
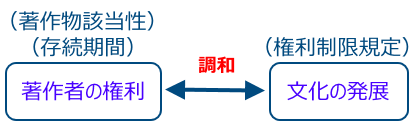
著作者の権利は、強力なものとして法定されていますが、著作者の権利を保護することにより著作者が受ける利益よりも、著作物を社会一般に流通させることにより社会一般が受ける利益の方が大きい場合には、著作権者の権利は制限されることになります。
また、創作はしたもののそもそも著作物としての保護に値しない場合や、長い年月がたって、保護される期間が終了するという場合もあります。
当HPについて
著作権法では、主に著作物として保護されるための要件や著作権者が有する権利、また、著作権者の権利を制限して許諾なしに著作物を利用できる場合について規定されています。しかしながら、その具体的な内容についてはよく分からないといった人も多いのではないでしょうか。
当HPでは、著作権法の規定をできる限り分かりやすく解説するコンテンツを用意しております。どうぞご参考になさってください。また、ご不明点についてはお電話にてご質問頂ければ、当所専門スタッフが丁寧にご説明申し上げます。
企業著作権担当者の方へ
- 他人の著作物の利用に際し(2019年05月13日)
- 疑似著作権について(2019年04月19日)
- 著作権管理者団体について(2019年04月09日)
- 著作権法30条(私的使用のための複製)と企業内小規模複製(2019年02月28日)
著作権制度

著作物と著作者
小説や絵画、音楽、映画など創作活動によって生み出された作品を著作物、生み出した人を著作者と呼び、日本では著作権法においてこれらに関する法整備が行われています。
著作物について
(1)定義に関する事柄
著作権法によれば、著作物は、その第2条1項1号で次のように定義されています。
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
人が作る物は様々ありますが、それらの中でこの定義に当てはまる物だけが、著作物として著作権法による保護を受けます。
しかしながら、この定義は非常に抽象的であり、これだけでは著作物の具体的なイメージがつかみにくいかもしれません。そこで、著作権法第10条1項各号が、著作物の例を示しています。
すなわち、
- ①小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物(1号)
- ②音楽の著作物(2号)
- ③舞踊又は無言劇の著作物(3号)
- ④絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物(4号)
- ⑤建築の著作物(5号)
- ⑥地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物(6号)
- ⑦映画の著作物(7号)
- ⑧写真の著作物(8号)
- ⑨プログラムの著作物(9号)
これらは例示ですから、ある物がこれらの例のいずれに当たるかが判然としなくとも(あるいはいずれにも当たらなくとも)、2条1項1号の定義に該当するものはすべて著作物として保護されることに注意しましょう。
ただし、一部の著作権法上の規定には、10条1項各号のいずれかに当たる特定の著作物を対象に定められた特則があり、その特則の適用を問題とする場合には、10条1項各号のいずれに当たるかを判別する必要があります。
(2)具体的要件について
著作物の定義から、著作物として保護されるために必要な4つの要件が導かれます。すなわち、①「思想又は感情」を含むこと、②「表現」されたものであること、③「創作性」があること、④「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であることです。
① 「思想又は感情」を含むこと
著作権法は、著作物の保護を通して文化の発展に寄与することを目的としているため、人間の精神的活動の成果といえるものでなければ保護されません。ただし、ここでいう思想又は感情とは高度なものである必要はなく、何らかの考えや気持ちが表現されていれば足りるとされています。
他方、人間の関与を受けていないものは、それが美的鑑賞に値するものであったとしても著作権法上の著作物とは認定されません。
② 「表現」されたものであること
著作者の頭の中にある思想や感情が、外部に認識可能な形で表現されてはじめて著作物たり得ます。外部から認識できない状態の情報は不明確であり法的保護に値しないからです。
このことから重要な考え方が導かれます。すなわち、著作物として保護されるものは、表現されたものに限られ、その表現を生み出すもととなったアイデア(思想、感情等)は著作物として保護されないということです。これを、表現・アイデア二分論といいます。
この考え方が著作権法の根底にあるため、ある著作物同士の表現の背景にあるアイデアやコンセプトが同じでも、具体的な表現態様が異なれば、著作権侵害とはなりません。
③ 「創作性」があること
著作権は、人間の知的な創作活動を奨励するための権利ですから、いかに苦労し、額に汗を流して生み出された物(たとえば、情報を収集し、単に時系列にまとめたもの等)であろうとも、知的な創作活動の成果といえなければ保護されません。すなわち、創作性が必要です。
とはいえ、この創作性の要件は極めて緩やかに判断されており、著作者の何らかの個性が表現されていればよいとされています。例えば、児童がクレヨンで描いた絵や、奇抜なところのない一般的な日記などにも創作性が認められます。
特許法における新規性や進歩性の要件が高度なものを要求していることと対照的です。
④ 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること
これは著作権が文化的所産を保護することを示しています。この点で、産業的所産を保護する特許法や意匠法と異なっています。
なお、本要件は文芸、学術、美術、音楽の4分野を挙げていますが、著作物として保護されるために、具体的にこれら4つのうちのどれに当たるかを特定する必要はなく、文化的所産であることが認められれば保護されます。
著作者について
(1)創作者主義とその例外
著作権法によれば、著作者は、その第2条1項2号で、「著作物を創作する者をいう」と定められており、著作物を現実に作成した者が著作者となり、その者に原始的に著作権が帰属します。これを創作者主義の原則と呼びます。
しかしながら、日本の著作権法には2点の修正が存在します。①職務著作(15条)と②映画の著作物の著作権帰属(29条)です。
① 職務著作(15条)…著作者の修正
これは、法人等の従業員が職務上著作物を作成した際に、一定の条件のもとで、その著作者を当該従業員ではなく法人等にする制度です。法人等が著作者になるため、すべての著作権も法人等が有します。
※なお、著作者と著作権者の区別に注意しましょう。著作物を創作した者が著作者であり、原則として著作権を有する著作権者でもあります。しかし、著作者の身分は一度発生するとその後変動はおこりませんが、著作権は譲渡等で帰属先が変動することがあるため、著作者と著作権者が異なる場合があります
このような修正が認められる理由は、使用者と第三者の保護のためとされています。
まず、使用者保護については、法人等の発意に基づいて職務上作成された著作物であるにもかかわらず、個々の従業員に著作権が帰属すると、法人等が当該著作物を利用する際に逐一それぞれの従業員から許諾を得る必要があり煩雑です。
また、業務に支障をきたす恐れがありますので、著作者を法人等とすることで使用者の円滑な事業活動を図ろうとしたものといえます。
次に、第三者の保護については、法人等の名前で公表された著作物に対する利用許諾を第三者が得たいと考えた場合に、著作権をその法人が有していた方が権利関係が明確であり、利用を円滑にすることができるとの考えに基づくものといえます。
② 映画の著作物の著作権帰属(29条)…著作権帰属先の修正
映画の著作物の著作権は、著作者である監督等ではなく映画製作者に帰属します。この場合、著作者と著作権者が異なることになります。ただし、著作者人格権は一身専属的な権利なので著作者である監督等に残ります。
このような修正が認められる理由は、第一に、映画の製作には巨額の投資が必要であるところ、その投資を行った映画製作者が投資に見合った経済的利益を得られるようにするためです。上映やビデオ化等の全ての権利を映画製作者に帰属させることで、映画製作者の投資回収を助けています。
第二に、映画は音楽の著作者、シナリオの著作者、絵画の著作者などなど多くの著作者が関与し、彼らが共同して作られた著作物であることが多いです。
そのため、映画の著作権を彼らの共有としてしまうと、一人の反対で当該著作物の利用ができなくなり(65条2項)、映画の著作物の円滑な利用が妨げられてしまうため、これを避けるための措置です。
各種権利
著作物は、著作者の思想や感情を表したものですから、その扱いについては著作者の人格的利益を尊重すべきです。同時に、「コンテンツ産業」と言われるように、財産であるという一面も持っています。
それぞれの側面から、著作者の人格的利益や著作物の財産的価値を守るため、各種の権利が定められています。これらの権利は、何もしなくても、著作物を作った時点で発生します(17条)。
著作者人格権
著作者人格権は、人格権ですから、著作者本人から誰かに移転させることはできません。
公表権(第18条)
著作物を勝手に公表されない権利です。
氏名表示権(第19条)
著作物自体又は著作物を提示するときに名前(本名、ペンネーム)を表示する/しないを決めることができるという権利です。
同一性保持権(第20条)
著作物とそのタイトル(題号)をそのままにしておき、意に反して変更、切除その他の改変を受けない権利です。
著作権
著作権は、財産権ですから、移転させたり、質権設定をしたりすることができます。
また、支分権といわれる下記に示す利用に関する権利を専有します。裏返せば、著作者の許諾がない限り、他人は支分権に示す行為を勝手に行ってはいけません(単に観賞したりする分には問題ありません)。
| 対象となる著作物(具体例含む) ※口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権以外は、条文上著作物の限定はありません | |
| 複製権 | 限定なし |
| ☆上演権 | 限定なし(演奏(歌唱を含む)以外の方法により演じること、例:演劇、舞踏・無言劇etc) |
| ☆演奏権 | 限定なし(楽器による演奏、歌唱) |
| ☆上映権 | 限定なし(映画、本、写真) |
| 公衆送信権等 | 限定なし |
| ☆口述権 | 言語(詩の朗読) |
| 展示権 | 美術(絵画・彫刻etc)、未発行の写真 |
| 頒布権 | 映画 |
| 譲渡権 | 映画以外 |
| 貸与権 | 映画以外 |
| 翻訳権、翻案権等 | すべて |
| 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 | すべて |
☆は無形的複製(→著作物の利用)
複製権(第21条)
著作物をコピーする権利です。
ここでいう「複製」は、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」(第2条1項15号)をいい、有形的でない再製は他の支分権に規定されています。
- 「有形的」ってどういうこと?
→記録媒体への固定など指します。演奏や放送は録音・録画しない限り形に残りませんので、無形的です。
- 暗号文を平文化するのは複製?翻案?
→暗号文と平文との間に実質的な差異(創作性における差異)がないので、複製にあたります。講演を原稿に起こしたり、曲を採譜したり、ソースプログラムを機械的にオブジェクトプログラムに変換するのも同様です。
- 一部を「引用するのはOK」と聞いたけれど…
→OKな場合もあります。
著作物の一部であっても、その部分に創作性が認められる限り、無断で複製することは複製権の侵害です。
ただし、著作権は「制限」を受けることがあり、その一つとして、「引用」があります(第32条)。→著作物の利用
上演権(第22条)
公衆に直接見せることを目的として著作物を上演する権利です。
→一般には不特定かつ多数の者を指しますが、著作権法においては「特定かつ多数の者」を含みます。従って、大学のゼミの構成メンバーは「不特定」とは言えませんが、「多数」と言えれば「公衆」に該当します。
演奏権(第22条)
公衆に直接聞かせることを目的として著作物を演奏する権利です。
ここでいう「上演・演奏」とは、生演奏等だけでなく、CD等から再生する行為も含みます。
上映権(第22条の2)
著作物を公に上映(映写幕その他の物に映写すること)する権利です。
→スクリーンに映写するものは全て含みます。スライドや、建物への写真の映写等。
公衆送信権等(第23条)
著作物を公衆送信したり、受信装置を用いて公に伝達したりする権利です。
公衆送信が自動公衆送信(インターネットなど)の場合、 送信を可能にすることもこれにあたります。
Eメールで特定人に送るのは「公衆」への送信ではないのでこれにはあたりません。
口述権(第24条)
言語の著作物を公に口述する権利です。
口述で録音されたものの再生や、電気通信設備を用いて伝達することも含まれます。
展示権(第25条)
美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物の本物を公に展示する権利です。
頒布権(第26条)
映画の著作物をその複製物により頒布(複製物を公衆に譲渡し、又は貸与すること)する権利です。複製物(フィルム)の配給制度を前提とした規定なので、原作品の頒布は含まれません。
映画の著作物の中に音楽等が含まれている場合には、それらを映画の複製物により頒布することもできます。
中古品も含めて流通をコントロールできる強い権利です。
→確かに「複製物」の頒布ではないので頒布権侵害にはなりませんが、公衆送信権の侵害となりますので、大丈夫ではありません。ちなみに、その侵害を知りながらダウンロードすることも侵害です(第30条1項3号)。
譲渡権(第26条の2)
著作物(映画の著作物を除く)の本物又はコピーを譲渡して、公衆に提供する権利です。
- 絵をプリントしたTシャツを仕入れて卸そうと思いますが、これも譲渡権侵害にあたりますか?
→元のTシャツを販売している会社が絵の著作権者から許諾を得て公衆に譲渡しているなら、それを更に譲渡するあなたの行為は譲渡権侵害にあたりません(第26条の2第2項1号)。これを「消尽」といいます。
- その販売元の会社がちゃんと適法に譲受しているか分からないのですが……
→もし譲渡権が消尽していなくても、譲渡を受けたときにそれを知らず、知らなかったことに過失がなければ、譲渡権侵害でないとみなされます(113条の2)。
貸与権(第26条の3)
著作物(映画の著作物を除く)のコピーを貸与して、公衆に提供する権利です。
翻訳権、翻案権等(第27条)
著作物を翻訳・編曲・変形し、又は脚色・映画化等、翻案する権利です。
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)
著作物を翻訳・編曲・変形し、又は脚色・映画化等、翻案することにより創作されたものを二次的著作物といいますが、もとの著作物の著作者は二次的著作物を創作した人と同じ権利を有します(ただし、もとの著作物の権利が及ぶ範囲に限定されるという考え方が一般的と思われます)。
著作隣接権
著作物を作った人だけが権利を得られるわけではありません。演じたり、放送したり、レコードを作ったりする人は、著作物を世の中に伝える役割を果たしてくれています。
もしそのような権利を保護しなければ、その人たちは利益を得られず、せっかく作った著作物も伝達されないことになっていまいます。
ですので、著作物を媒介してくれる人々にも、著作権法上の権利が認められています。
| 実演家の権利 | レコード製作者の権利 | 放送事業者の権利・有線放送事業者の権利 | |
| 氏名表示権 | ○ | - | - |
| 同一性保持権 | ○ | - | - |
| 複製権 | - | ○ | ○ |
| 録音権・録画権 | ○ | - | - |
| 放送権・有線放送権 | ○ | - | ○* |
| 送信可能化権 | ○ | ○ | ○ |
| テレビジョン放送の伝達権 | - | - | ○ |
| 商業用レコードの二次使用料を受ける権利 | ○ | ○ | - |
| 譲渡権 | ○ | ○ | - |
| 貸与権など | ○ | ○ | - |
| 保護期間 | 実演が行われたときから50年 | 音源の発行が行われたときから50年 | 放送/有線放送が行われたときから50年 |
* 放送事業者については再放送権と有線放送権、有線放送事業者については放送件と再有線放送権
<ページ内コンテンツ>
著作権支援室 著作物の利用 著作権の登録・契約 外国制度 トラブル回避